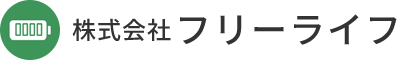停電に強い家庭用蓄電池の選び方を解説
京都市は、豊かな自然と悠久の歴史・文化が息づく都市として知られています。しかし、自然の猛威は、そうした都市にも容赦なく襲ってきます。台風や豪雨による被害はまだ記憶に新しいことでしょう。とくに停電が発生すると水道まで止まってしまう家庭もあり、生活への影響ははかり知れません。そこで今回は、停電時に役立つ家庭用蓄電池の選び方などについてご紹介します。京都市にお住まいで、自然災害対策を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. 京都市:自然災害とその対策

京都市は、京都府の南部に位置する府庁所在地であり、政令指定都市です。市内を賀茂川や桂川、宇治川が流れ、豊かな自然の息吹を感じられます。また、悠久の歴史や伝統に裏打ちされた文化や芸術を身近に感じ、その奥行きの深さを楽しむことのできる街です。
1-1. 最近の自然災害被害状況
観光名所でもある日本の古都・京都ですが、自然災害の影響を避けることはできません。ここでは近年発生した自然災害についてご紹介します。 2017年10月21日から23日にかけて京都市を通過した台風21号は、以下のような被害の爪あとを残しました。
- 軽傷者:4名
- 停電:約2,440軒
- 避難勧告:23学区、避難準備等:42学区
- 道路被害:全面通行止め22件
- 建物被害:一部破損5軒
- 文化財被害:雙ケ丘1件、二条城2件
- 文教施設被害:建物23件
また、2018年9月4日から8日にかけての台風21号での被害は以下のとおりです。
- 停電:約5,500軒
- 建物被害:床上浸水1棟、一部破損1棟
- 道路被害:規制中の道路1件
- 避難勧告:西京区、右京区など
1-2. 京都市の地震対策
次に、京都市の地震対策についてご紹介します。京都市は地震対策に力を入れており、耐震診断や耐震改修の助成制度を行ってきました。また、市内の建物の耐震化を進めるため、密集市街地対策も実施しています。市民には、日頃からの備えとして、家具の固定や避難経路の確認を奨励してきました。
1-3. 京都市の水害対策
京都市は水害対策として、ハザードマップを公開し、浸水想定区域を明示しています。また、集中豪雨による地下施設への浸水対策も行っています。市民には、雨水の排水口の清掃や、避難場所の確認を呼びかけてきました。
1-4. 京都市の土砂災害対策
土砂災害に対しては、危険箇所の調査と対策工事を実施しています。市民には、土砂災害警戒情報の確認や、避難行動の準備を促してきました。また、地域ぐるみの防災訓練も行い、災害時の対応力強化に力を入れています。
1-5. 京都市の防災教育と訓練
京都市は防災教育にも力を入れており、学校や地域での防災訓練を実施しています。市民には、家庭での備蓄や応急手当の習得を推奨してきました。また、防災ノートや防災カードを配布し、災害時の行動計画を作成するよう呼びかけています。
2. 停電時に活躍:家庭用蓄電池の役割と活用方法

前の章でご紹介した京都市の自然災害では、多くの家庭で数日間にわたる停電が発生しました。最近、一般家庭でできる停電への備えとして、家庭用蓄電池が注目されています。
2-1. 非常時の電力供給を担う
家庭用蓄電池は、停電時に電力会社からの送配電網から離れて、家庭内で電気を自家消費することで電力を供給します。この機能が「自立運転モード」です。
また、家庭用蓄電池には、以下のタイプがあります。
- 全負荷型…家全体に電力供給可能
- 特定負荷型…特定の部屋だけに供給
全負荷型はIHコンロや、電圧が200Vの大型のエアコンも使用できます。停電時でも普段と変わらない生活を送れるのです。一方の特定負荷型では、IHコンロや200Vのエアコンは使用できません。設置費用は安くなるのですが、必要最低限の電力供給となります。 また、次の点に注意しておきましょう。
- 停電に備えて蓄電量をつねに20%以上残しておく
- 蓄電池は一時的な電力供給源であり、長期間使用するなら太陽光発電との併用の検討が必要
2-2. 家電に優先順位をつけておく
停電時には、蓄電池から電力を供給する家電製品に優先順位をつけておく必要があります。蓄電池の容量によっては、すべての家電を同時に使用することが難しいからです。そのため、携帯電話や冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・照明など、生活に欠かせない家電を優先的に使用することが重要です。 とくにエアコンは消費電力が大きいため、蓄電池の容量を考慮し、どのタイミングでどの程度使用するかを事前に計画しておきましょう。
2-3. 長時間の停電に備えるには:太陽光発電との併用
長時間の停電には、家庭用蓄電池と太陽光発電システムを組み合わせた「創蓄連携システム」が安心です。日中は太陽光発電で生成した電力を使い、夜間は蓄電池に蓄えた電力を利用できます。 平常時は、太陽光発電で生成した電力を使用しつつ、蓄電池に電力を蓄え、余った電力は電力会社に売電します。夜間に昼間蓄えた電力を使用できるので、電気代の節約にもつながるのです。
3. 停電に強い家庭用蓄電池の選び方

家庭用蓄電池は、突然起こる停電で頼りになる存在です。ここでは、停電時に役立つ家庭用蓄電池を選ぶ際のポイントについて解説します。
3-1. 「容量」がポイント
蓄電池を選ぶ際には「容量」に注目しましょう。その容量が、使用する家電の出力をカバーできるかがポイントです。以下に主な家電の標準出力をご紹介します。
- 電子レンジ…1,500W
- 冷蔵庫(40L)…190W
- エアコン…(暖房時)750W、(冷房時)650W
- テレビ…150W
- 照明…100W
次に、家庭用蓄電池の必要容量算出の計算式をご紹介します。計算式は「使用する電化製品の出力(W)×使用時間(h)=必要な電力量(Wh)」です。 たとえば、冷房や照明・テレビを5時間使用する場合、上の計算式に当てはめると、必要な電力量は4,500Wh(4.5kWh)です。また、4人家族の1日あたりの電気使用量は約18.5kWhで、停電時に最低限必要な容量は6.5〜7kWhと言われています。この容量があれば、1日中停電しても最低限の生活が可能です。 このようにして、家庭用蓄電池の必要容量を計算してみましょう。
3-2. 家庭用蓄電池の種類で選ぶ:「定置型」がおすすめ
家庭用蓄電池の種類は、以下の2種類があります。
- ポータブル蓄電池…小型・持ち運び可能
- 定置型蓄電池…蓄電容量が大きく、太陽光発電と連携可能
停電時に使用することを考えると蓄電容量の大きい定置型蓄電池を選ぶ方がよいでしょう。
3-3. 停電時に自動で切り替わるものを選ぶ
停電時には「自立運転モード」に切り替えて、家庭用蓄電池の電力を使えるようにしなければなりません。その際、機種により自動で切り替わるものもあれば、手動で操作しなければならないものもあります。 自動切替機能のある機種は、停電発生後約5秒で蓄電池からの電力供給に切り替わります。予期せぬ停電時の混乱によるトラブルを避けるため、自動切替機能があるものを選ぶとよいでしょう。